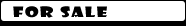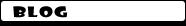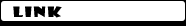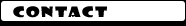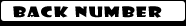色の世界標準を創案したマンセル
■マンセルの肖像とサイン (1858~1918 米)
■均衡色立体(1905)
■色の系統樹(1905)
■『Orr氏の肖像』
マンセル作
マンセルは肖像画家でもあったが、確認されている絵は数少ない
さまざまな表色系を尋ねる上で、まず基本タイプを挙げておきたい。大きくは4種ある。
1.色名による表し方:JIS物体色の色名」の系統色名などあり、誰にも分かりやすい。
2.色票による表し方(顕色系、カラーオーダーシステムと呼ぶ):代表的には世界標準の「マンセル表色系」と、ヨーロッパで普及している「NCS(Natural Color Svstem)がある。
日塗工『塗料用標準色』はマンセルに準拠しているため、ここに属する。
3.光の数値による表し方(数値混色系と坪ぶ):代表に「xyz表色系」があり、色を精密に表示できるため、全ての古色系の中核に位置づけられる。「RGB表色系」と、色違い(色差)の表示で利用される均等住空間「L*a*b*表色系」と「L*u*v*表色系」もこれに属する。
4.その他特定目的のための体系:配色調加が目的の「Hue&Tone」と呼ばれる色相とトーンの2属性による体系に「CCIC(商工会議所カラーコーディネーション・チャート)」、「PCCS(日本色研配色体系)」があり、他に市場調査、流行色分折等を目的とする体系が多数ある。
この通り、利用目的によって多種類の色体系が生み出された。上述の1、2、3を定規の目盛りに例えて言えば、色名は10cm単位で子供用、マンセルは1cm単位の大人用、xyzは1mm単位の専門家用となろう。
20世紀に人り世界標準とし万の表色系開発が本格化する。マンセルが1905年に発表の著作「色彩表記法」は、いわば最初のファンファーレであった。
彼はボストンに生まれ、マサチューセッツ州立師範学校を卒業、以後、没年まで母校の美術教師を勤めた。当時のアメリカは資源が豊富な一方で熟練労働力に欠き、国策として教育に力が入れられた。マンセルも初等教育に使命感を持ち、色彩教育法開発に取り組む中で子供にも理解される色体系が創案された。
マンセルは色が成り立つ属性を3つ挙げ、それぞれを記号と数字で尺度化し、立体像に組み立てた。三属性は略してHVCとも呼ぶ。
色相(Hue,略号H)-色みの違い
明度(Valuc,略号V)-明るさの度合い
彩度(Chroma.略号C)-鮮やかさの度合い
色相は5原色を設定し、回転円盤の混色で無彩色となる関係を反対に配置して色相環を構成した。明度は独自に開発した測定器を用いながら白と黒の間をなだらかに分割した。彩度は純色と無彩色を混合しながらわずかな違いを弁別する方法が繰り返され決められた。このとき色相によって純色の位置が一定でないことが分かり、色立体全体はいびつな形となる。
彼は学生時代に物理学者O.N.ルードの『近代色彩論』を愛読、ルードを師と仰いで、色彩を研究テーマの一つとした。ルードは日曜画家で、その立場から画家にも分かるように色の原理を解き、絵具名で反対色の関係を示す色彩環が画家に重宝がられた。また絵具の3原色のほかに、光の3原色があることも知られるようになった。この仏語訳がスーラ、シニャックをはじめ後期印象派の画家に広く読まれ、シュヴルールと並んで画壇に大きな影響を及ばした。
マンセル没後は、科学者の子息アレクサンダーに継がれて1929年に大著『Munsell B00K of Color(マンセルブック)』が発行された。
やがで1931年に「xyz表色系」が制定されると、光学的な数値と対応できるよう見直た改定がなされ、国際照明]委員会(CIE)で世界標準に採択された。日本では1958年以降「JIS Z 8721色の表示方法-三属性による色の表示」としてマンセル表色系が色彩業務に関わる人に不可欠となっている。
■ひと口知識 『 画家としてのマンセル』
彼は大学を主席で卒業、留学資格を得てパリの画塾と国立美術大学に在籍、サロン(官展系美術展)に出品、さらにカトU-ヌ・メディチ奨学資格でローマに留学したエリ-トで、帰国後には肖像画スタジオを開設した。 だが画家としては色彩業績にかき消され、今日では美術辞典にも登場しない。ここに極めて珍しい彼の画業を紹介しておこう。
モデルは夫人の父銀行家のOrr氏である、彼は色彩調和論にも強い関心を示し、1905年には調和論で著名なオストワルトとも懇談している。だがその論述に至らぬまま生涯を閉じた。
■20色相の三次元模型
■100色相環 ■等色相面
10基本色相をさらに10分割した色相環
縦に明度、横に彩度を配置した5YRの等色相面
▲ このページの上へ